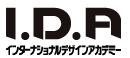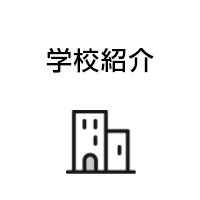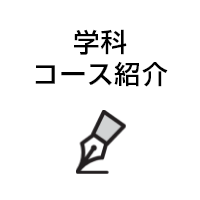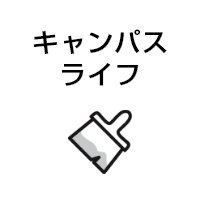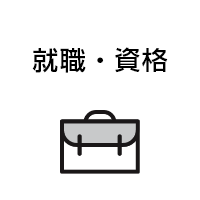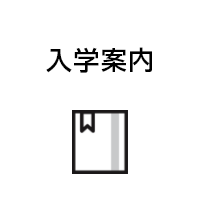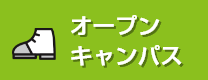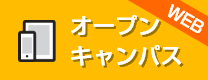2024.04.01
東京オリンピックや大阪万博で建築士の仕事が多くの注目を集めるようになりました。建築士とはどのような仕事?必要な資格や年収について紹介
【コラム】建築士とは
TVやインターネットでも建築士のことが度々話題になり、建築士とはどのような職業か気になる人も多いでしょう。
この記事では建築士の仕事や必要な資格、年収や建築士になるための方法について紹介します。
建築士の職業に興味がある人は、この記事を読んで建築士の概要を理解しましょう。
建築士とは簡単にいえば建物を設計して工事を見守るプロ
建築士を一言で説明すると建物を設計して、その工事を見守るプロフェッショナルです。それぞれの業務についてより細かく見ていきます。
建築する建物の構造や工事方法などを設計する
建築士の仕事内容といえば、この設計業務をイメージする人が多いでしょう。
建築する建物を木造にするか、鉄筋コンクリート造にするか、材質は何にするか、部屋の数や配置はどのようにするかなどを、お客さん(建築業界では「施主」といいます)と打ち合わせて決定します。
その際、工事の予算や法的な規制、実際に建物ができたときの眺望や景観などを、施主がイメージしやすいように打ち合わせを進めることも建築士の大切な仕事です。
そうして施主と打ち合わせて決定された内容を、ハウスメーカーや工務店などのいわゆる大工に引き継ぐため、設計図に落とし込みます。ここまでが建築士の設計業務です。
設計図に従って工事が進んでいることを監理する
設計業務が終わっても建築士の仕事は終わりません。
設計業務が終わった後も、その設計図のとおりに工事が進んでいることを建築士は確認しなければなりません。
設計図の中で明らかな矛盾や誤りがある場合は、工事を行う業者から指摘が入り設計の見直しをする場合もあります。
また、誤りとまではいかなくとも、工事業者から設計について質問される場合もあるでしょう。
それらの質問に対して適切に回答をして、工事を滞りなく進めることも建築士の仕事です。
さらに、質問がなくとも工事が適切に設計書に従って進んでいるか、工事業者が設計図や施主の意向を無視して工事を進めていないかなども建築士は確認する必要があります。
このように設計業務のあとも、建築士の仕事はまだ続くことをぜひ知っておきましょう。
行政の手続きや契約書作成などの事務処理も行う
施主は建築の法律や条例に関して知識がないことがほとんどです。
そのため、施主に代わり行政への手続きや契約書の作成などの事務処理を建築士が肩代わりする場合もあります。
これは不動産を販売する業者が行う場合もあれば、工事を実施する業者が行う場合もあり、建築士・不動産会社・工事施工業者などの役割分担によって担当する業務が異なります。
また、企業の中で建築士として働く場合には、企業の中でも役割分担が異なる場合もあるでしょう。
そのため、所属する企業や役割の中で建築士として行う業務も少しずつ変わる可能性があることを覚えておいてください。
建築士になるためには国家資格の取得が必要
建築士になるためには国家資格の取得が必要です。一般的な建築士の資格は一級建築士と二級建築士です。
それぞれ免許の交付をする部門の違いはありますが、どちらも国家資格として認められており、この資格を取得しなければ建築士として業務はできません。
では、一級建築士と二級建築士にどのような違いがあるのか、それぞれの資格について詳しく見ていきましょう。
一級建築士は大きくて広い建物を設計できる
一級建築士は建築する建物に制限がないことが特徴です。
大きくて広い建物、たとえばオフィスが入るビルやショッピングモールなどの商業施設から、オリンピックや世界大会に使われるような競技施設まで、どのようなものでも建築に関われます。
もちろんこれよりも小規模な建築物である戸建て住宅や、小さいアパートやマンションの設計や構築も可能です。
このように制限なくさまざまな建築物の建築に関われる資格が一級建築士の資格です。
二級建築士は戸建て住宅の設計がメイン
二級建築士は主に小規模な戸建て住宅や集合住宅をメインとした建築を行う人向けの資格です。
二級建築士は一級建築士と違い、設計できる建物に制限がかかります。
具体的には木造建築物なら3階建てまで、建物の高さは16mまで、延べ面積は300㎡までになります。
※参考:国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」
このように、一級建築士とは異なり、設計に関われる建物に制限があることが一級建築士と二級建築士の大きな違いです。
そのほかにも特殊な建築士がある
一級建築士と二級建築士のほか、木造建築士の資格もあります。
木造建築士は二級建築士よりも設計できる建築物にさらに制限がかかります。
しかし、この木造建築士の資格は一級・二級建築士とはやや別物の資格として考えましょう。
具体的には木造建築士の資格は木造住宅を建てるための資格というよりも、築年数の古い木造建築、たとえば神社仏閣などの設計や工事を監督するための資格だと考えましょう。
一級・二級の建築士でも及ばない木造建築物に対しての知識を持ち、特殊な木造建築物の対応を行う資格が木造建築士と考えれば区別がわかりやすく区別できます。
一級建築士の平均年収は700万円
建築士の仕事内容や資格について理解したところで、その年収についても確認します。
令和4年度の「賃金構造基本統計調査 」によると、一級建築士の収入は年収で約620万円です。
国税庁発表の平均年収が約458万円だったことを考えると、一級建築士の収入は非常に大きいものだといえるでしょう。
二級建築士の収入は官公庁による公式なデータは公開されておらず、一般的には一級建築士よりもやや低めだと考えられます。
しかし、一級建築士の収入の高さを考えると、二級建築士の収入も平均より低いことは考えにくいでしょう。
また、二級建築士を持つ人は実務経験を積み一級建築士の資格取得を目指す人も多いことから、収入も一級建築士のものが参考になります。
建築士の仕事が無くなる可能性は低い
高い収入を得られる建築士の仕事について、将来性を心配する声もあります。しかし、建築士の仕事が無くなる可能性は低いと考えて問題ないでしょう。
たしかに少子高齢化で住宅需要が減少したり、AI技術の発達により設計業務をAIが行えるようになる時代がくる可能性はあります。
しかし、どれほど少子高齢化が進もうとも、人がいる限り住宅の需要が無くなることはありません。
また、AI技術が発達して設計業務をAIが行えるようになったとしても、施主の希望をヒアリングしてAIにその希望を伝え、施主の希望が正しくAIの設計に反映されていることを判断する人が必要です。
さらに、AIでは窓から見える眺望、家の外観が人の気持ちに与える影響などを考慮できません。
AIを使いこなせる建築士であれば、今後も仕事が無くなる可能性を心配する必要はないでしょう。
建築士になるには指定科目を学んで試験の合格が必要
建築士になるためには、指定された科目を学んで試験に合格する必要があります。
二級建築士は資格取得が一級建築士ほど難しくありません。
建築系の学校で定められたカリキュラムを履修して卒業すれば受験資格が得られるほか、学校に通わずとも7年の実務経験を積むことで受験資格を取得できます。
どちらの場合でも受験資格を取得し試験に合格すれば、二級建築士の資格を取得できます。
一級建築士になるには実務経験も求められる
ただし、規模の大きい複雑な建築物の設計にも携われることから、一級建築士の資格取得の難易度は二級建築士の資格取得難易度と比べてやや高めです。
建築系の学科を卒業し、定められた年数以上建築の実務に関わらなければ一級建築士の資格を取得できません。
学科と実務、両方の試験に合格する必要もあり、その資格取得難易度は決して簡単とはいえないものになっています。
将来も仕事に困らない一級建築士を目指すならインターナショナルデザインアカデミー
あなたがもしも一級建築士を目指していて、将来も仕事に困りたくないならぜひインターナショナルデザインアカデミーを進学先の候補に入れてください。
インターナショナルデザインアカデミーなら初心者からでも仕事に困らない一級建築士を目指せます。
AIに仕事を奪われない建築士になるためには、人にしかできない仕事を行うことが大切でした。
たとえば、施主の希望をしっかりと聞いてそれを叶えるためのヒアリング能力やデザインセンスです。
インターナショナルデザインアカデミーでは、ゼロからのスタートでも建築やインテリアのデザインセンスが身に付くカリキュラムで授業が行われるため、抜群のデザインセンスを身に付けて卒業できます。
さらに、企業とのコラボによる実践的な授業やコンテストへの応募などを通じて、施主へのヒアリング能力や、チームで仕事を行うためのコミュニケーション能力が身に付くため、AIでは代わりのきかない建築士になれるでしょう。
将来仕事に困らない一級建築士を目指したい人は、ぜひインターナショナルデザインアカデミーを進学先候補としてご検討ください。